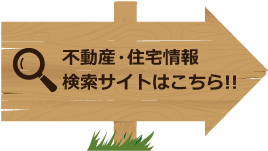管理体制・規約のチェックポイントは?

どんなに立派なマンションでも、管理がおろそかだと建物や設備の劣化のスピードが早まり、資産価値が下がってしまいます。マンションの管理状況や、共同生活のルールを定めた管理規約の事前チェックは必須です。
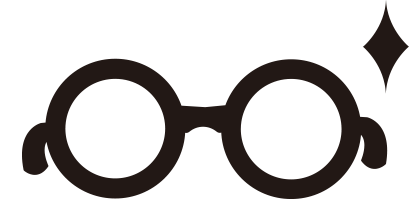 このページの見どころ!!
このページの見どころ!!
【管理体制】をチェック
マンションの価値は、管理体制で決まる

中古マンションを選ぶ上で、大切なポイントとされるのが「管理体制」。マンションの管理体制を見ずに決めてしまうと、入居後に思わぬトラブルや不満を抱える可能性もあります。
物件見学時には、どうしても住戸の中ばかり目がいきがちですが、共用部分の管理状態もチェックして、管理のよいマンションを選ぶようにしましょう。
共用部分の清掃は行き届いているか?

共用部分がきちんと清掃されているか、故障や不具合が放置されていないかを確認します。たとえば、「エントランスやエレベーターホールのゴミや汚れが目立つ」「植栽が手入れされていない」「共用廊下の電球が切れている」「駐輪場の自転車やバイクが整理されていない」…などは、管理がおろそかになっているサイン。住人が日常的に利用する機会の多い共用部分ほど、入念に確かめましょう。
管理形態や管理費の状況は?

多くのマンションでは、マンション管理にかかわる清掃や点検・修繕、会計といったすべての業務を管理会社に任せる「全部委託管理」の形態を採用しています。全部委託管理だと毎月の管理費は高いですが、住人の負担は少なくなります。また、数は少ないものの、点検・修繕など一部の業務のみ管理会社に任せる「部分委託管理」や、住人がすべての管理を行う「自主管理」もあります。部分委託管理や自主管理は住人が共用部分の管理に携わるため、それなりに手間がかかります。毎月の管理費や管理形態はもちろん、管理費の内訳、管理費の滞納の有無なども購入前に確認できるので、仲介会社を通して管理組合に問い合わせてみましょう。
マンションの管理形態
| 管理形態 | 特徴 |
|---|---|
| 全部委託管理 | すべての管理業務を管理会社に委託するため、住人は管理の手間が不要。管理費が最も高い |
| 部分委託管理 | 一部の管理業務を管理会社に委託し、残りは住人が管理を行うことで、管理費を抑える |
| 自主管理 | 管理会社に頼らず、住人がすべての管理業務を行う。3つの管理形態のうち、管理費は最も安いが、住人の負担が大きい |
管理人の雰囲気や勤務形態は?

物件見学時にマンション管理人と顔を合わせる機会があれば、挨拶がてら、マンションでの生活や共用部分の使い方などについて質問してみるとよいでしょう。管理人の言葉づかいや態度がよく、気軽に話しやすい雰囲気だと、入居後になにか困ったことがあっても気軽に相談できます。また、管理人の勤務形態には「常駐管理」「日勤管理」「巡回管理」の3種類があります。このうち、常駐管理は24時間体制のため緊急時の対応が迅速で、防犯面も安心ですが、管理費は最も高くなります。日勤管理・巡回管理の場合は、管理人の勤務時間や、勤務時間外の連絡窓口があるかどうか確かめておきます。
管理人の勤務形態
| 勤務形態 | 特徴 |
|---|---|
| 常駐管理 | 管理人が住み込みまたは交代で管理業務を行う。管理費は最も高いが、夜遅くの帰宅時や、緊急トラブルが発生したときの安心感がある |
| 日勤管理 | 管理人がマンションに通勤し、勤務時間内に管理業務を行う。土日や年末年始などは休みになることが一般的 |
| 巡回管理 | 管理人が決められた曜日の一定時間のみマンションに滞在し、管理業務を行う。時間が限られている分、管理費は最も安い |
修繕計画や積立金の状況は?

マンションでは、年数の経過とともに生じる傷みや不具合を修繕するために、12~15年の周期で大規模修繕工事を実施します。この大規模修繕工事に備えた長期修繕計画や、次の修繕工事の時期、修繕積立金の積み立て状況なども、仲介会社を通して管理組合に尋ねてみましょう。毎月の修繕積立金の金額が妥当かどうかも確かめておきたいポイントです。修繕積立金が不足していると、修繕積立金が上がったり、まとまった金額の一時金が必要になることもあります。
日頃の点検やメンテナンスは?

大規模修繕工事だけでなく、日頃の点検や定期的なメンテナンスをしているかどうかも確認しましょう。建物や設備の劣化のサインを見逃さず、適切に修繕することで、マンションの寿命や住み心地が変わってきます。
マンションの管理規約は?

マンションの管理規約とは、マンションのすべての住人が気持ちよく暮らせるよう、共同生活のルールや決まり事をまとめたものです。一部の規約(用途制限など)については重要事項説明書に記載があり、口頭でも説明されますが、この先のマンション暮らしにかかわることですので、購入前に必ず管理規約や使用細則を入手し、目を通しておくようにしましょう。
【リフォームのしやすさ】をチェック
入居前や将来のリフォームに備えて、リフォームの自由度を調べる

近年、築年数の古いマンションを購入して、自分好みにリフォームを行う人が増えています。思いどおりのリフォームを実現するには、その物件の状態はもちろん、「リフォームがしやすいかどうか」にも注目しましょう。
マンションの場合、リフォームやリノベーションができるのは専有部分に限られ、その範囲もマンションごとに規約で定められています。マンションの構造によっては希望するリフォームができない場合もあるため、事前の確認は必須です。
間取りの変更がしやすい構造か?

「建物の構造・共用部分のチェックポイントは?」で説明したように、マンションの建築構造には、壁式構造とラーメン構造の2つがあります。中低層マンションに多い壁式構造は、壁や床などで支える構造のため、壁の移動や撤去が難しいことがあります。一方で、中高層マンションに多いラーメン構造は、柱や梁で支える構造のため、壁をすべて取り払って間取りを大きく変えるなど、リフォームの自由度が高くなります。
マンションの建築構造
| 耐震性 | 構造 | 特徴 |
|---|---|---|
| 高←←←→→→低 | 壁式構造 | 壁・床・天井の「面」によって建物部分を支える構造で、ラーメン構造よりも耐震性が高い。室内に柱や梁の出っ張りがないので見た目がスッキリするが、取り払えない壁が多く、間取り変更をともなうリフォームがしづらい。中低層のマンションで多く採用される |
| ラーメン構造 | 柱や梁によって建物部分を支える構造。壁式構造に比べて構造上必要な壁が少ないため設計の自由度が高く、間取り変更をともなうリフォームにも対応しやすい。その一方で、壁式構造よりも耐震性は低め。室内の柱や梁の出っ張りが目立ちやすく、家具配置が難しいことも |
□水回りの移動がしやすい構造か?

キッチン・浴室・トイレなどの水まわりの移動は、排水管が通る床下のスペースの状況によって移動のしやすさが変わってきます。マンションの床下の排水管には勾配がついており、縦管と呼ばれる共用の配管に向かって水が流れています。床下のスペースに一定の広さがあれば排水管の勾配がつけやすいので、水まわりの大幅なレイアウト変更が可能。その一方で、築年数の古いマンションだと排水管が階下の天井裏を通っていることが多く、水まわりの移動が難しくなります。また、床下が狭いと排水管の勾配をつけらませんが、その場合は床を上げて排水管のスペースを確保する方法もあります。
□リフォームができる範囲は?

マンションは専有部分と共用部分に分かれており、このうち居住者がリフォームできるのは専有部分にあたる居室内部のみ。コンクリートの壁・床・天井などの構造部分や、バルコニー、玄関前のアルコーブ、ポーチ、廊下は共用部分となり、居住者が手を入れることはできません。玄関ドアや窓サッシも外側は共用部分なので勝手に交換できませんが、ドアの内側を塗り替えたり、内窓を取り付けたりすることは可能です。マンションによっては、専有部分でもリフォームできる範囲が決まっていることがあります。騒音の問題によりフローリングの遮音等級が指定されたり、フローリング自体が禁止というケースもあるので、事前に管理規約や細則を確かめましょう。
□工事ができる曜日や時間帯は?

新居のリフォーム計画が立ったら、管理組合に工事の申請を行います。リフォーム工事は資材の搬入や騒音をともなうため、工事ができる曜日や時間帯の制限を設けているマンションも多いです。
【ペットの飼育ルール】をチェック
ペットとの快適な生活を実現できるマンションを選択

ペットと一緒に暮らしている人や、これからお迎えする予定のある人が必ずチェックしたいのが、マンションのペット飼育ルールです。
物件広告に「ペット可」とあっても、飼育可能なペットの種類や頭数などに制限がある場合がほとんどです。必ず事前に管理規約や細則に目を通して、ペットとの暮らしに支障がないか確かめておきましょう。
飼育できるペットの種類・サイズ・頭数は?

管理規約を見て、飼育できるペットの種類(犬・猫・小動物など)・サイズや体重の制限・頭数の制限などを確認しましょう。犬なら小型犬のみ可能というマンションや、飼育可能な犬種があらかじめ決まっているマンションなどもあります。
ペットのための共用施設などはあるか?

最近では、ペットと住人が快適に過ごせる「ペット共生型」をアピールポイントにしたマンションも増えています。ペット共生型のマンションでは、共用施設として屋外にペット専用の足洗い場やペットの汚物を流せるトイレ、ドッグランを設けたり、ペット飼育可能なフロアとペット飼育禁止のフロアを分けたりする工夫も見られます。
ペット飼育のルールは?

ペットと暮らす飼い主はもちろん、ペットを飼育していない住人も快適に暮らせるように、敷地内でペットを歩かせてよい場所や、飼育する際の届出義務、ワクチンや健康診断の義務、ペットの飼い主で構成されるコミュニティ(ペットクラブ)の加入義務などのルールが決まっています。
 まとめると…
まとめると…
管理の良し悪しで住み心地が変わる。購入前に管理状況を確かめよう

「マンションは管理を買う」というフレーズがあるように、管理の良し悪しは建物の寿命や住み心地に直結するポイントです。購入前に現地を訪れて清掃などの管理状況を確かめたり、修繕計画や管理規約に目を通したりして、管理体制の整ったマンションを見定めましょう。
コラムを探す
新着コラム
最終更新日 2025年10月31日

- 中古マンションは魅力が多い一方で、経年による建物や設備の劣化は避けられず、管理状態の良し悪しが資産価値に影響するなど、注意点があるのも事実。購入してから後悔しないために、中古マンション購入前に確認すべきポイントを押さえましょう。

- 都内近郊の住まい探しは、土地の広さ・住環境のよさ・コスト面など、23区にはないメリットがいくつもあります。都内近郊の人気エリアやおすすめエリアの特徴、交通利便性や平均価格など、住みたい街が見つかるヒントをお伝えします。
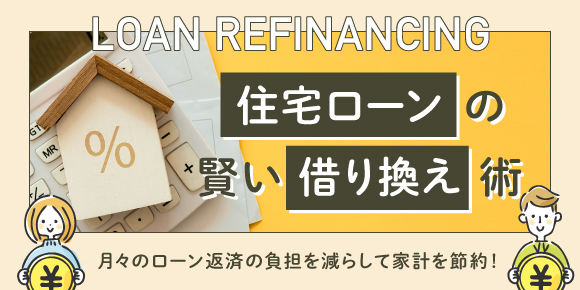
- 現在返済中のローンよりも低金利のローンに借り換えをすれば、支払う利息の負担を減らすことができます。借り換えに向いているケースの見極めや、借り換え時の注意点など、住宅ローンの賢い借り換え術をマスターしましょう。
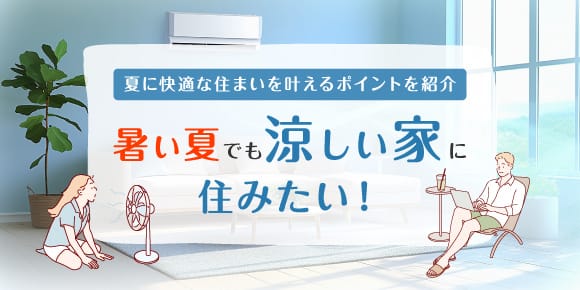
- 夏でも涼しい家づくりのポイントをご紹介。断熱・気密や日射遮蔽の対策を行うことで、家の中でエアコンなどの冷暖房器具をあまり使わずに気持ちよく過ごせるようになり、光熱費の節約にもつながります。

- 田んぼや畑といった「農地」を売りたい・買いたい・転用したい……というときに、かかわってくるのが「農地法」という法律。農地法の基礎知識や、農地の取り扱いのポイントを知り、スムーズな売買や転用につなげましょう。

- 新しい住まいを探すときに、「どこに住むか」は重要なポイント。都内の各エリアや23区の特徴、気になる利便性や平均価格など、住みたい場所を見つけるヒントをまとめました。
- 住まいの情報ナビ
- 住まい探しのコツや建物の知識
- 中古マンション購入の失敗・後悔を防ぐポイントをチェック!
- 管理体制・規約のチェックポイントは?